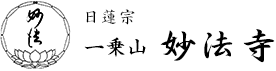2016年08月08日
法話
人として生を受け、老いて、病んで、死を迎えます。生老病死の過程は誰もが避けて通ることはできません。
身体をいただいた以上、やがて世を去る時が訪れます。母もこれに逆らうことなく、平成28年5月11日 享年91歳。 波瀾万丈の人生を静かに閉じました。
母、寿美子は父、安田信好と縁あって結婚し、5人の子供に恵まれました。
父は、還暦を機に、自分史「一筋の道」を刊行しました。そに中に安田家の人生の分かれ目となる出来事が記されています。「昭和33年、松の内も明けた日曜日であったと思います。塚本三郎さんがわざわざ坂下町(岐阜県)の我が家を訪ねられ、『4月から是非愛知県の方へ変わって来てほしい』と懇請されました。『次の衆議院選挙には必勝態勢で臨んでいる。法座のほうが手薄になるから、何とか代わりをしてほしい。安田さんが真に法華経の教えを求めて修行されるなら、是非この機会に愛知県に来てほしい』と力説されました」と。
この時父33歳、私、小学5年 11歳でした。私達一家は山奥の岐阜県から当時の愛知県知多郡上野町へ引越しをしてきました。翌年には伊勢湾台風の暴風雨で住宅が被害を受け、修復中近くの町営住宅(家族7人、四畳半二間の生活、2年程)へ一時避難をしました。この時に祖母は長男の家を飛び出して、我が家へ転がり込んできたのです。
祖母は当時のことを振り返り、遺稿集「花散りぬ」の中でこう綴っています。「私が久好の家を飛び出して、世話になりに行ったのですから、信好夫婦にとっては大変な迷惑であったと思います。二間きりの部屋の四畳半に私が寝ますので、上の2人の孫は押入れに寝ていました。狭いながらも楽しい我が家となるように、私なりに務めたつもりです」と。祖母との同居の決断は、父の親孝行(法華経に導く)の真価が問われた時期であったと思います。
このようなわけで祖母との同生活が始まりました。母にとっては居心地の良い環境ではなかったと思います。すべての面において祖母に勝ものはなく、楽しい我が家となるわけがありません。祖母とのぎくしゃくしている頃のことでした。母は、鉄板のプレス加工をする町工場で働いていました。ある時作業中に、機械に両方の指を挟まれてしまったのです。この時のことを祖母は遺稿集の中で、「いつの年だったか寿美ちゃんが会社で両手の怪我をして、お勝手一切のことができなくなり、洗濯から買物、5人の孫たちの世話まで大忙しでした」と、語っています。祖母によって助けられたこともありましたが、母は一層肩身の狭い思いをしていました。
祖母は同居後、その後の生活を遺稿集の中で「その頃から法華経の話を信好から聞き、朝晩のお勤めも孫たちと一緒にやるようになりました。そして信好から法華経の書写をやるようにすすめられ、白折れ、色紙、筆等用意してくれました。毎日たとえ一頁でも一行でも書くように努めてまいりました」と。祖母は私達家族との同居を機に法華経を学び、お題目を唱えるようになりました。今にして思えば、祖母は、釈尊に堤婆の如く、母の将来の為に、損な提婆達多の役割を演じて修行をさせたと思うのです。
それから20年後、昭和57年には妙法会の新道場が雉子野に建ち、両親は新たな人生を歩むことになります。将来、妙法会会長夫人となる等誰も想像しなかったことです。愚痴の多い母でしたが、法華経に人生を捧げた父を陰で支え、祖母を法華経に導いた影の功労者だと思うのです。当に、泥田の中に白蓮華の花が咲き、煩悩の中に菩提心(信仰の心)が育ったのだと思いました。
かくして、昭和61年11月14日祖母は享年85歳の人生を閉じることになりますが、最後四カ月は病院での闘病生活を余儀なくされました。遺稿集の中で祖母について私は、「一刻な祖母であったが、初孫である私はよくかわいがってもらった。≪中略≫思えば祖母自身は自らの煩悩を四カ月の闘病生活で果たすことになったと思う」。最後は、つらく当たった母に一番面倒をみてもらうことになった。祖母は病床よりすべてを母にゆだね、「おかあさん、おかあさん」と甘え、「すまんねえ、すまんねえ」と詫びを言った。母も喜んで祖母の介護をした。これも一重に法があったお蔭だと思います。祖母は病むことを通して、法悦を得る素晴らしい縁を与えていただいたのだと思います。
母は、提婆の役を演じた祖母を看取り、二年後お世話になった師匠塚本たし先生の介護にも三年近く関わり、見送っています。
母の苦労は晩年になり報われました。母の臨終の姿と、屈託のない笑顔の遺影がそれを物語っています。